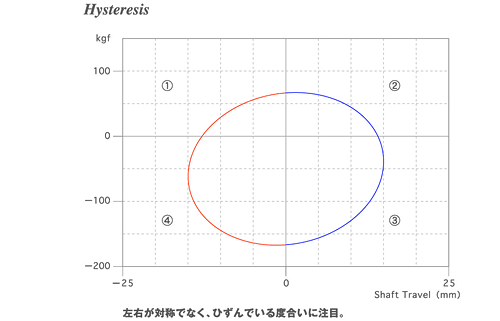例えば、1本のダンパーでCOMP減衰力特性と言っても、縮み始めてから縮み終わるまでの過渡特性は、油圧的な残圧を伴なって始まり、また残圧を残しながら終わるので、イコールにはなりません。この油圧的な0点の歪みをヒステリシスと言います。 このように、油圧部品であれば避けられないヒステリシスは、減衰力のアジャスターによって歪められ、さらに発生される残圧(またはエネルギーが立ち上がる遅れ)が、機械的な作動フリクションに追加される形でヒステリシスを増大させます。 |
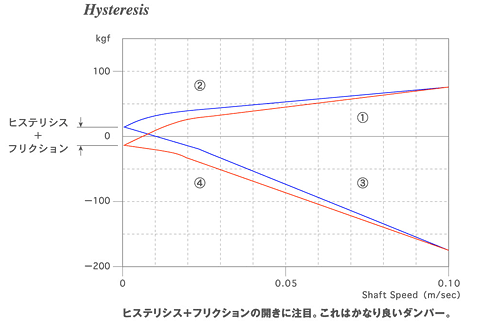 |
|
QRSのレースダンパーは、昔からメインピストンの減衰力を70%~90%に設定し、リザーバータンク側のセカンドピストン(=ハイスピードアジャスター)を追加的に10%~30%を組み合わせて全体の減衰力としてきました。 ところが、90年代半ばから2000年前半にかけてのトレンドは、メインピストンの設定やバルブはいい加減でも、セカンドピストン側のハイスピードアジャスターによって減衰力はいかようにでもなりますよ、とやっていました。 ヒステリシスは、機械的な作動フリクションも映し出します。 |
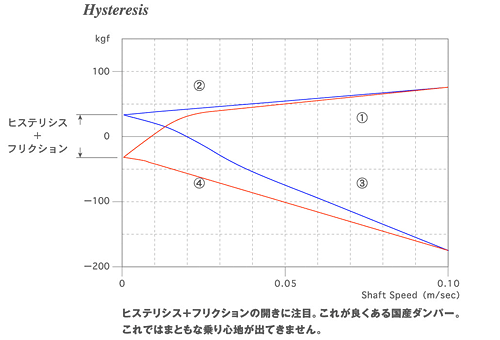 |
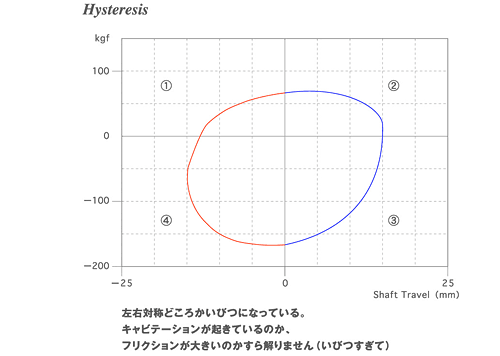 |
例えば、アウディRS6(V8 Twin Turbo / 4WD)用のダンパーがあったとします。 でも、もうおわかりかと思いますが、これほどまでの減衰力の差を1本のダンパーでまかなうためには、ダンパーの機械的なキャパシティをターゲットとする減衰力の高い側(RD=500kgf)に合わせる必要があります。それは減衰力の低い側(RD=100kgf)のダンパーにとって過剰なキャパシティです。 逆にターゲットとする減衰力が RD=35kgfのダンパーをシミュレーションしてみましょう。 このフリクションの差は、サーキットで縁石に乗って曲がって行くときの走破性にも通じるところです。 |
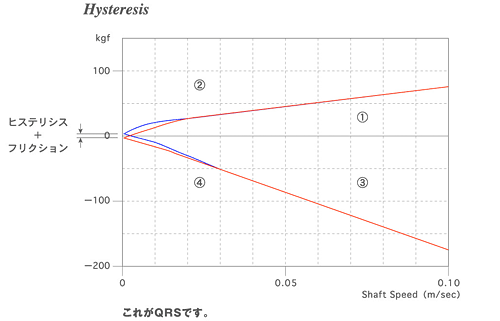 |
|
|
||||||||
 |
|
||
|
||
| HOME|TECHNOLOGY|AUTOMOTIVE|MOTORCYCLE|DEVELOPMENT|MAINTENANCE|CONTACT US|DOWNLOAD クァンタムの速さの秘密|クァンタムの正しい選び|新しい4輪のクァンタム|新しい2輪のクァンタム|セットアップ|レベリングシステム 新しいセッティングへアップデート|メンテナンスは重要です|サイトマップ|会社案内|お問合せ |
Copyright (C) Quantum Racing Suspension. 2010. All Rights Reserved. |